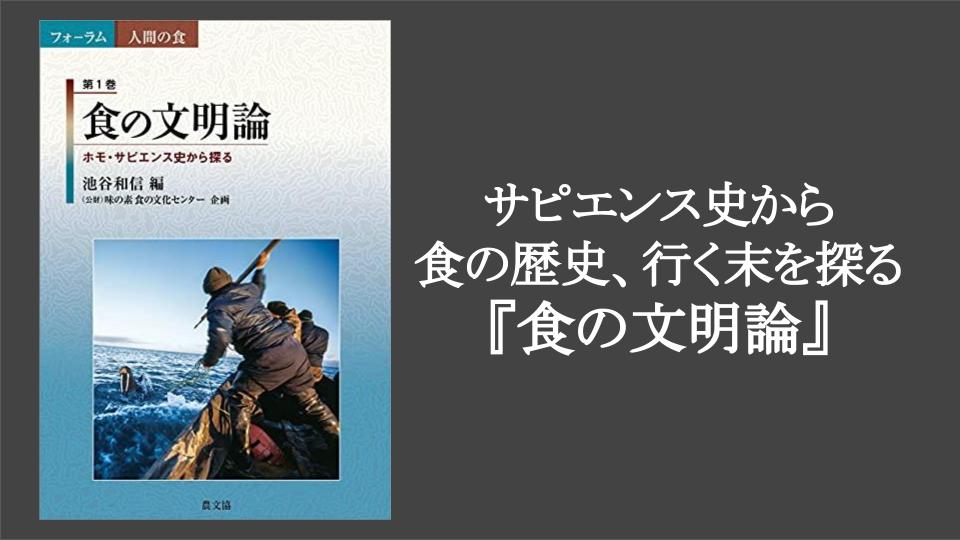コロナ禍は私たちの食を大きく変えた。飲食店は営業自粛の要請を受けた。外出自粛の要請や来日者の激減で閉店した店や、テイクアウトやデリバリー、通販のみに切り替える店も多くあった。自粛要請が解除された後でも営業時間の短縮や大人数での利用、アルコール飲料の提供の自粛が要請された。店の入口には消毒液と体温計の設置が当たり前になり、効果があるのかわからないアクリル板がテーブルを埋め尽くすようになった。
同じテーブルで、大皿の料理を分け合うこと、会話をしながらの食事など、それまで当たり前であったことはできなくなった。現在ではある程度緩和されているが、現在でも消毒液は置かれているし、またいつ自粛を要請されるかわからない状態である。そしてこれは一生続く可能性もある。
コロナによって私たちの食を取り巻く環境は大きく変わった。コロナ禍を経験した私たちの食は、今後どうなっていくのだろうか。食の変容は私たちの生活や価値観にどう影響していくのだろうか。この予測は簡単ではない。そうであるからこそ、人類の食に関する長く、大きな歴史を今一度振り返り、これまでの食、現在の食を振り返ることが重要になるのではないか。その試みをするのが『食の文明論』である。
本書によれば、食の歴史を振り返る本はこれまでたくさんあったが、現代文明の行く末という問題意識のもとにホモ・サピエンス史の視点から食を正面から取り扱うものはこれまでなかったという。本書はいわば、私たちの食がどこからきて、どうなり、そしてどこへ向かうのかを展望する壮大な一冊であるといえる。
今なぜ、食のホモ・サピエンス史のアプローチが必要なのだろうか。一言でいえば、コロナ禍の現代において私たちの将来の生活が、どのようになるのか予想がつきにくくなっているからである[ダイアモンドほか二〇二〇]。人が生きていくうえで食は欠かせないが、近年、食をめぐる環境が大きく変わってきた。現代は、将来予測のつきにくい社会であるからこそ、ホモ・サピエンス史の視点から食の現在や未来を展望することが不可欠になるであろう。
付け加えるなら、コロナ禍によって変わった食の現状を考察にいれた著書は多くはなく、その意味でも重要な一冊であるといえる。
内容紹介
ではどのようにサピエンスの歴史から食の文明を語るのだろうか。本書では、次の3つの切り口からアプローチする。
- 食資源の開発
- 食の技術と食事空間
- 食と現代社会
第一部では「食資源の開発」に触れる。食資源の開発とは、食料の獲得、生産である。ここでは狩猟採集民、牧畜民、農耕民、都市民、それぞれについて章を設け、それが始まった時期や、それぞれの生活の特徴を考察する。いうなれば、私たちはどのようにして食べ物を生産してきたかである。
また第一部の最後では都市民の食についても話題にする。都市民とはつまり、食料の生産に携わらない人のことである。私たちの多くがそうであるが、都市民はどのようにして誕生したのか、その説明からはじまり、さらに食べ物を他人に提供する場としての飲食店のはじまりについて触れている。
第二部の「食の技術と食空間」では、食材の加工と、食事をする空間についてである。具体的には、調理、料理について、そしてそれらを行うキッチンという空間、キッチンで使う道具である調理器具、そして食事をする空間について、その長い歴史と現代的問題について触れる。
最後、第三部では食と現代社会である。人類が辿ってきた肉食の歴史と、現代の肉食が抱える問題の論からはじまり、都市部の人間と途上国の人間の栄養代謝の話題、インスタント食品が私たちに生活に与えた影響、人間に特有の共食にかかわる話題として「食とコミュニケーション」についての話題である。ここでは私たちが見ず知らずの人がもってきた食べ物を食べることができ、また知らない人のために食べ物を集めてくるという他の動物には見られない行為について論じている。
なぜ人間は見ず知らずの人が作った料理を平気で食べられるのか?
最後の章の「食とコミュニケーション」では、これまで出版されてきたサピエンス史を振り返る著書を強く連想させる部分がある。
本章では人類の食に決定的な特徴として、食べる時に集まることが挙げられるとしてる。もちろん現在では1人で食べることも多いが、それでもやはり、折に触れては集まって食事をする。人類が1人で食事をするようになったのはほんの最近の話で、家族や仲間と集まって食事をするのが基本である。一方で他の霊長類にそのような行為は見られないという。
長い間サルやゴリラと付き合っていると、人間の食事がとても不思議な現象に思えてくる。現在約四五〇種いる霊長類の仲間で、人間のように食べる時に集まる種はいない。
さらに驚くのは、人類は何日も離れ離れになっていても仲間のことを覚えているし、その仲間が遠くから運んできた食べ物を平気で食べることだ。これは人間に特有の行為だという。他の類人猿は、自分が見ていない場所から運ばれてきた食べ物を平然と口にすることはしないという。まずは警戒するという。
都市に住む多くの人は、見ず知らずの人が生産し、調理し、運んできた物を食べている。料理をする場合であっても、基本的に野菜や果物、肉や魚は見ず知らずの人が作っている。料理に使う調味料は誰がどのように加工したのかをまったく知らない。調理器具に関しても、ガスコンロや包丁、鍋など、それらが安全に利用できるという前提でいる。これができるのは私たち人間がある種の信頼関係を築いているからだろう。
この信頼関係はお金、法律、倫理といったものによって支えられている。ユヴァル・ノア・ハラリのいうところの虚構である。
ユヴァル・ノア・ハラリはサピエンス全史のなかで、人類は虚構を語り共有することによって、より大きな集団関係をまとめてきたと述べている。虚構とは、宗教や思想、倫理などとも言い換えることができる。私たち人間が、顔を一度もみたことがない、肌の色や言語、宗教が異なる人が作った食べ物を平気で食べられるのは、手元に届く食べ物は安全に違いないという虚構を信じているからだ。虚構を語り、信じる能力によって私たちの多くは食料生産以外の仕事ができるようになったのである。
それを伝えてくれる本書『食の文明論』は、サピエンス全史のようなサピエンスの歴史をつかむ壮大な著書と並ぶ、スケールの大きな一冊なのではないだろうか。