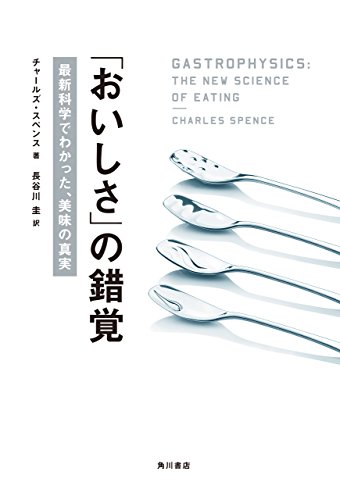なぜポテトチップスの袋はうるさいのか?
あんなにもガサガサ音がする袋なのだろか?
実は、袋の音が大きければ大きいほど、ポテトチップスがサクサクしているように感じられるからだそうだ。
オックスフォード大学の学生のアマンダ・ウォンと行った研究を通じて、食べているときに耳にするガサガサというパッケージの音が大きければ大きいほど、人々はポテトチップス自体をよりサクサクしていると感じることがわかった。
「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実(チャールズスペンス)
他にもサクサク感を強調したスナック菓子は、必ずといっていいほど音がする袋を採用している。菓子だけなくシリアルでも。
ポテチの袋の例からわかるように、人間はまったくおなじ食べ物であっても、音が違うだけで食べ物に対する評価がわかる。
空腹のときに食べる唐揚げはめちゃくちゃうまいが、満腹のときの唐揚げはたんなる油のかたまりだ。
こういった味覚の錯覚、デタラメさを浮き彫りにしてくれるのが、『「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実』という著書だ。

「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実 (角川書店単行本)
- 作者:チャールズ・スペンス,長谷川 圭
- 発売日: 2018/02/28
- メディア: Kindle版
著者はチャールズスペンスという心理学者で、味覚の研究にもたずさわる。
彼は2004年に、ポテトチップスを噛みくだいたときの音を増幅させると、人は自分が食べているポテトチップスを実際よりもサクサクで新鮮であると感じる、ということを実証しイグノーベル栄養学賞を獲得した。
本書は、そんな著者がこれまでの研究であきらかにした、認知が味覚にどのような影響を与えるかを紹介する一冊である。
本ページではその書評をしていく。
匂い、音、色などの情報は料理の評価に影響する
あるレストランで、カニのリゾットのつけあわせとして、カニ風味のアイスクリームをだしたそうだ。しかしその評判は、「まずい」「しょっぱい」などさんざんだった。
というのもこのアイスクリームは淡い赤色をしており、この色から多くの人はフルーツ系の甘い味を期待していたという。
しかし実際に食べたら、カニ風味のしょっぱいアイスだ。カニ味のアイスクリームを食べ慣れた人でなければ、そんなもの美味しくいただけるはずかない。
しかしこのカニ風味アイスは、ある工夫をすることで評価を一変させた。それは名前を変更すること。
「塩味のアイスクリーム」もしくは、「フード386」というミステリアスなネーミングにして提供したそうだ。その名前や描写をきいた人は、事前情報なしに食べた人よりも満足度が高かったという。
このように人間は、自分がイメージしている味と実際の味が違うと、酷評してしまう。逆に慣れていない食べ物であっても、その食べ物の詳細を描写する名前や解説があると、事前イメージと実際の味が一致し、評価も良くなるというのだ。
こういった、認知によって味の感じ方や、料理に対する評価が変わるという例が本書ではたくさん解説されている。参考までにその一例は要約して列挙しいく。
- 匂いをつけたり、かえたりすると、味の感じ方がかわる
- 料理の盛り付けや、色をかえると、味の感じ方がかわる
- お皿の形、料理の形によって味の感じ方がかわる
- 料理の食感や音(パリパリなど)によって料理の評価がかわる
- お店のBGMによって料理の評価や売れる商品がかわる
- カトラリーの重さによって料理の評価がかわる
- レストランの内装によって売れる商品が違う
以上は本書で紹介されている一例だ。また変わる傾向があるというもので、絶対的な影響があるというわけではない。
ただしこういった影響は、味覚を職業としているワインソムリエであっても受けてしまうらしい。
いわく、まったく同じワインを、着色したものとそうでないもので飲み比べてもらったら、評価がかわったというのだ。
人間の味覚は、他の要素に影響されるのだ。たとえワインソムリエであっても。
遺伝的に知覚できる匂い・味に違いがある
さらに驚くべきことに、遺伝によって味や匂の知覚がかわるという。
たとえばアンドロステロンという物質の匂いについて、2人に1人がこの匂いを感じないそうだ。
アンドロステロンとは、ステロイドの一種である。
この匂いを人口の35%が汗臭いと感じ、15%の人は甘い花の香り、ムスクのような匂いだと感じるというデータがある。
おなじ物質でもまったく匂いを感じない人、不快な匂いだと感じる人、いい匂いだと感じる人がおり、そしてこれは遺伝的に決まっているという。
またこれは味についてもあてはまる。
たとえば一般的な人より味覚が繊細な人として、「超味覚者」が存在するのがそのいい例だ。他にもブロッコリーの苦味を感じることができる人とそうでない人がいるらしい。
ある特定の味や匂いを良いと思うか悪いと思うかは、経験や慣れによっても決まるだろう。しかしながら遺伝的に決まっている部分もあるというのは驚かされる。
これはつまり、嫌いな食べ物が嫌いであるまさにその理由は、遺伝的な要因にあるからかもしれないということだ。
人間は料理を「味」以外の要素で評価している
味覚に直接関係する大脳皮質の領域は1%ほどしかないそうだ。
つまり人間のあらゆる知覚のなかで、味覚はそれほど重要ではないということだ。味覚よりも嗅覚や聴覚の方が役割がおおきい。
われわれは1つの料理を評価するとき、味から判断しようとする。
しかしわれわれが感じる味は、聞こえる音や触った感覚、食べ物の色、グルメサイトでの星の数や値段といった事前情報から影響を受けている。
つまり、われわれは料理を味だけでなく、匂いや触感、音や情報から、無意識的に、判断しているということだ。
たしかに好きな人と食べるものはなんでもおいしい。高級な料理であっても嫌いな上司と食べるものはおいしくない。
店員の態度や異臭のするお店、雑音がおおい店で食べる料理は、どれだけ新鮮で高級なものであってもおいしくない。
「美味しい」とはなにか?
本書を読んでわかるのは、われわれが味覚からえている情報はごく一部にすぎないということだ。
人間はさまざまな要素から料理の味を評価しているし、味以外の要素が料理の評価を左右している。われわれは思っている以上に、味を正確に判断していないのだ。
ならば「美味しい」というのは、たんなる味の良い・悪いではなく、もっと総合的な、味とそれ以外の要素が自分にとって良いか悪いかであるといえるだろう。
これはつまり、どんな食べ物でも、工夫しだいで、あるていど美味しくなるということを意味している。
味がそれほど良くなくても、見た目が良ければ、匂いが良ければ、周りの音が心地よければ、お店の雰囲気が良ければ、好きな人と一緒なら、美味しいと錯覚することができるのだから。

「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実 (角川書店単行本)
- 作者:チャールズ・スペンス,長谷川 圭
- 発売日: 2018/02/28
- メディア: Kindle版